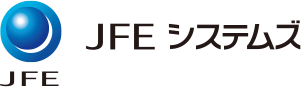スマートファクトリー推進のためJ-PROCUREを導入し、調達業務をすべて電子化しました。月5,400件に上る購買管理が効率化され、全工場で年間3,700時間の削減が見込まれています。
日本最大の電炉メーカーであり、H形鋼生産量で国内トップシェアを誇る東京製鐵株式会社(以下、東京製鐵)は、J-PROCURE(ジェイ・プロキュア)を使って購買管理システムを刷新し、本社購買部門と全工場資材部門で活用されています。
システム刷新の経緯とその効果について、同社 執行役員 宇都宮工場長 グリーンEV鋼板事業準備室長 酒井 久敬氏(写真左)、宇都宮工場 管理部長 船曳 晋哉氏(写真右)、同管理部資材課係長 中山 佳郁氏(写真中央)に詳しくお話を伺いました。
東京製鐵の業態
- 東京製鐵の事業内容について教えてください。
東京製鐵は1934年に創立した電炉メーカーです。建物、自動車、家電などから発生する鉄スクラップを様々な高付加 価値製品に再生(アップサイクル)しています。国内トップシェアのH形鋼以外にも、ホットコイルや厚板等の高炉メーカーが得意とする鋼板品種も生産、最近ではグリーンEV鋼板の自動車産業向け量産供給を目標とした活動も行っています。
東京製鐵では、2017年に「Tokyo Steel EcoVision2050」という長期環境ビジョンを制定し、脱炭素社会と資源循環社会の実現を目指しています。高炉材に比べわずか5分の1と圧倒的にCO2排出量が少ない電炉材の提供を通じて社会全体のカーボンマイナスと、鉄スクラップのアップサイクルによる資源循環に貢献したいと考えております。
従業員数は1,028人(2022年3月31日現在)、売上高は270,883百万円(2022年3月期)です。

「Tokyo Steel EcoVision2050」
ロゴマーク
J-PROCUREの活用状況
- J-PROCUREをどのように活用されていますか。
J-PROCUREのベースモジュール、スポット購買モジュール、リピート購買モジュールを使って購買管理システム(社内名称「KATTE」)を構築し、2021年11月から宇都宮工場で稼働させました。2022年4月から本格運用を開始し、本社購買部門と全工場(宇都宮・田原・岡山・九州)の資材部門、取引先で活用しています。
J-PROCURE導入前の課題
~月5,400件の購買管理が全て紙ベースだった
- J-PROCUREの導入を検討された経緯について教えてください。
「Tokyo Steel EcoVision2050」の段階的目標として、2030年度に600万トンの生産 (2021年度生産量の約2倍)を掲げています。それを現在の人員で達成するために、業務を合理化する「スマートファクトリー推進プロジェクト」を各部署が進めており、購買・資材部門では購買管理システムの刷新を最大のテーマとしました。
従来の購買管理は、約30年前に構築した基幹システムで行っていました。発注の起案から上長の承認、取引先への発注、検収まで全てが紙ベースで、基幹システムへは現場の購入依頼を見ながら手入力していました。まさに昔ながらの調達業務です。
そのため、以下のような課題がありました。

「『KATTE』を稼働させたことで、Tokyo Steel EcoVision2050の実現に一歩前進することができました」酒井氏
1.業務が遅延する要因に
紙ベースの承認フローだったため、上長の不在時は承認印がもらえず、業務が止まってしまいました。また、月に5,400件もあるので書類の回覧や進捗確認に時間がかかっていました。
2.業務負荷が高い
工場受入後に、本社購買部が納品書ベースで検収をしていましたが、月末月初の伝票照合に多くの時間を費やし、業務負荷が高くなっていました。また、購買関連の書類はファイリングして保管していましたが、本社ではスペースが足りず工場に送って保管していました。そのため、会計監査の際に必要な書類を保管場所から探し出すのもひと苦労でした。
3.工場間で業務フローが統一されておらず、購買管理システムも個別運用していた
工場ごとに製造品が異なることから特有の購買ルールが設定され、購買管理システムも個別に運用していました。しかし、基幹システムは長年の運用でブラックボックス化しており、システム改修を工場間で横展開できずにいました。
以上の課題を解決するために購買管理システムを刷新することにしました。
購買管理システム導入の要件
~製造業向けのパッケージ製品であること
- どのような要件で購買管理システムを選定されましたか。
以下の3つの要件で比較検討しました。
1.製造業向けのパッケージ製品であること
コストを抑えて短期構築するために、パッケージ製品を導入したいと考えていました。手を加える箇所が少なければ少ないほどコストを抑えられますので、同業での実績がある製品を探していました。
2.全業務を電子化できること
業務効率をアップするために、取引先を含めて、発注から検収まで全ての調達業務を電子化することを条件にしました。そのためには東京製鐵だけでなく取引先でも使ってもらえる操作性の良い製品であることも重要でした。
また、承認フローを電子化して、どこにいても承認が可能であること、進捗確認も容易であることも要件に加えました。

「JFEシステムズのサポートがあったので、工場ごとに異なっていた業務フローをスムーズに統一することができました」船曳氏
3.基幹システムと連携できること
今回、基幹システムから購買管理を切り出すことになりますが、それ以外は従来通り基幹システムで行います。そのため基幹システムとのデータ連携がスムーズに行えることも必要でした。
まずは、カタログベースでピックアップした製品から2製品に絞り、デモを見せてもらいました。
- デモではどのような点を確認されましたか。
大きく2点を確認しました。1つ目は、現在の業務プロセスとの差異がどの程度あるのかの確認です。2つ目は、既 存の帳票データを入れた実機を使わせてもらい操作性などを確認しました。
以上の要件で比較検討した結果、J-PROCUREは同業他社での導入実績があり、機能面でも優れていたため、J-PROCUREを導入することにしました。また、サーバーなどのインフラ構築もJFEシステムズに一括して依頼しました。
スムーズに導入するための3つの工夫
- スムーズに導入するためにどのような工夫をされましたか。
「スマートファクトリー推進プロジェクト」による理念先行型のシステム刷新だったので、まず、親しみを持ってもらえるように新システムの愛称を募集しました。発注部門からの「買って!」という依頼に対して、購買・資材部門として「きちんと買う」ことができるようにということで、「KATTE (KobAi Transformation To E-Procurement System)」と名付けました。
そして関係者全員の方向性を統一することも重要だと考えました。そのためJFEシステムズとの要件整理のミーティングには、本社購買部門、工場資材部門、システム部門が参加して意見を出し合ってもらいました。特に工場特有の業務フローを統一するために、工場資材部門には管理職から担当者まで全員が参加してもらい、要望の取りこぼしがないようにしました。
さらに、工場ごとに説明会を開いて疑問を解消したり、全工場の担当者がJFEシステムズに出向いてJ-PROCUREを操作させてもらいながら説明を受けたりしてJ-PROCUREに対する理解を深めてもらいました。
これらの取り組みにより、「KATTE」構築から本稼働に至るまでスムーズに進めることができました。
取引先に対してもスムーズに使ってもらえるように、入力項目を最小限に抑えるなど、誰でも利用しやすいように配慮しました。また、操作マニュアルやQ&Aを作成して共有すると同時に、操作手順を動画撮影して分かりやすく伝えるようにしました。稼働後も、随時Q&Aを更新して共有することで、想定よりも早く問合せが収まりました。
導入効果
~どこにいても承認ができ、意思決定が迅速化
- 「J-PROCURE」を導入した効果について教えてください。
「J-PROCURE」の導入により、以下のような効果が出ています。
1.年間3,700時間の削減
月5,400件の購買管理が電子化されたことで、全工場で年間3,700時間の削減を見込んでいます。月次作業で何百枚もの書類を見ながら入力を行っていた担当者は、その作業がなくなったことで、時間が余っていると自ら申告してくるようになったほどです。
2.意思決定の迅速化と見える化の実現
承認フローの電子化により、上長がどこにいても承認を得ることができるのでリードタイムの短縮化につながっています。また、発注フローの見える化により、依頼した発注が今どの段階にあるのかを容易に把握できるようになりました。

「JFEシステムズは当社の要望に対し、蓄積された知見や他社事例を踏まえてよりよい形で提案をしてくれました」中山氏
3.完全ペーパーレス化
全ての調達業務をWeb上で行うことで完全ペーパーレス化を実現し、書類運送にかかるCO2排出量削減に寄与しています。また、従来の保管スペースの有効活用も出来るようになりました。
4.業務フローの統一化
全工場で同一システムを利用することで、従来は工場ごとの運用になっていた業務フローを統一することができ、内部統制の観点からも好ましい形になりました。
5.ホストコンピューターの負荷軽減
従来の購買管理システムは、ホストコンピューターのリソースを大きく消費していました。そのため更新の度にスペックを上げて対応していましたが、今回のシステム刷新によりダウンサイジングすることができました。また、従来は工場ごとに購買管理システムの保守をしていましたが、一元管理ができるようになり保守の負担も軽減しました。
JFEシステムズのサポート
- JFEシステムズのサポートはいかがでしたか。
JFEシステムズは選定段階から、各工場のヒアリングに同席してJ-PROCUREの説明をしてくれました。また、全ての質問に対してQ&Aを作成し、機能面についての質問についてはパッケージでの実現方法など、カスタマイズが最小限で済むように提案をしてくれました。いつも、システムに精通した者にしか分からない資料ではなく、システムに不慣れな所属担当者でも理解しやすい資料を作って提示し、こちらが驚くくらい丁寧に回答してくれました。 このようなJFEシステムズの親身なサポートのおかげで、早い段階で新たな購買管理システムについてのイメージを持つことができました。
- J-PROCUREに対する評価はいかがですか。
上長がどこにいても承認を得ることができ、進捗状況も即座に確認できるので、所属担当者や最終決裁者の役員からも高い評価を得ています。また、取引先からも使いやすいと、操作性の良さを評価してもらっています。
今後の取り組みの予定とJFEシステムズに対する期待
- 今後の取り組みのご予定を教えてください。
直近ではインボイス制度に対応していく予定です。今回は購買管理に特化したためストック管理モジュールは導入しませんでしたが、今後、導入することでさらなる業務効率化が図れるのではないかと考えています。タイミングを見て検討したいと思っています。
- 今後のJFEシステムズに対する期待について教えて下さい。
現在、発注の数量・金額が適正かどうかを分析するためにエクセルでデータ加工をしていますが、J-PROCUREでそれができるような仕組みがあればいいなと思っています。
また、本社で集中購買している副原料や一部副資材の購買はシステム化が進んでおらず、業務効率化が課題となっています。JFEシステムズには知見を踏まえた最適なシステムの提案を期待しております。今後ともよろしくお願いいたします。
- お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。
※ この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。数字の一部は概数、およその数で記述しています。